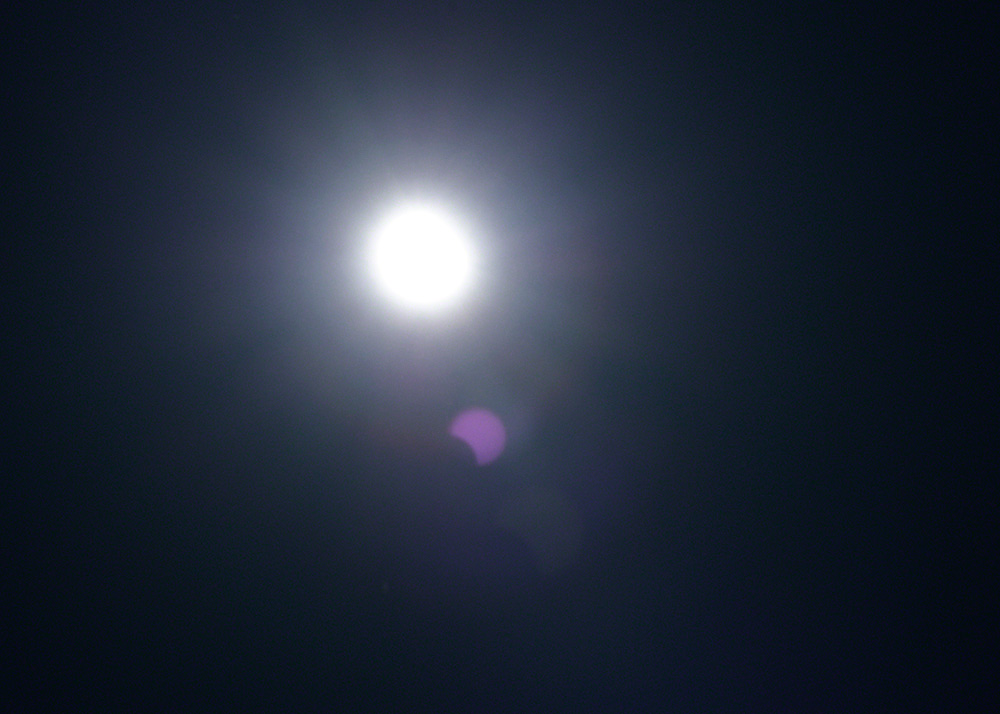旅の相棒、フォード・マスタング。
(6th generation)GT Premium Fastbackというグレードのモデルだった、たぶん。。
3.7リッターのV6自然吸気エンジンから、300hp/380Nのパワー&トルクを発生させる。
アメリカン・マッスルカーの一角を占めるクルマとししては、それほど驚くようなスペックではないけれど、もっとパワーが欲しければ、5.0L / V8エンジン搭載のモデルもあるし、昨今のエコ指向に振った2.3L / 4気筒ターボ・エンジンのモデルもある。
ドイツ車の同じようなカテゴリーのクルマにはV6やV8のNAエンジンはもはや皆無だし、V6のNAエンジンで、この排気量あたりのFRクーペといえば、パッと思い浮かぶところでは、レクサスのRC350くらいか。。
そのレクサスRC350は、ジャーマン・スリーのDセグメントをターゲットにしているようで、マスタングと競合する気はあまりナイみたい。
そういう意味で、このマスタングというクルマ、シボレーのカマロやダッジのチャレンジャーあたりと競合するだけで、海外のライバルのことは考えてないらしい。
というより、そのサイズやスペックから考えて、アメリカ国内向けのドメスティック・カーという意味合いが強いか。
そんなドメスティック・カーでしかないのに、子供の頃からこのクルマの存在は知っているし、だからこそ、このクルマを旅の相棒に選んだわけだし、つまり異国の旅人にこのクルマを借りさせようというだけのブランド・ヴァリューがあるということがスゴいところなんだろう。
実際走らせてみると、エンジンのレスポンスが少しダルなフィーリング。
このあたり、いかにも大排気量のNAエンジンのクルマを走らせている感があって、一般的になんとなく想像しているアメリカ車の印象を裏切るモノではない。
ただアクセラレーターを踏めば、その分だけキチンとトルクが盛り上がるし、NAエンジンならではの気持ちいいフィールを味わえる。
しかし、走らせる前にイメージしていたほどの迫力はナイ。そこはやはり3.7リッターというエンジンのキャパシティなり。
おそらく5.0L / V8エンジンのモデルに乗れば、いかにもなアメリカン・フィーリングを体験できるのかもしれない。
逆にこのクルマのデザインは気に入ってるけれど、ガス・マイレッジが・・という層には、2.3L / 4気筒エコブースト・エンジンのモデルを選べるようになっている。
そう考えれば、この3.7L / v6モデルというのは、両方のイイとこ取り、バランス・モデルというところか。
まぁ、うまくセグメンテイションされている、といっていいのだろう。
全体的には、決してノンビリしているというほどではないけれど、だからといって乗り手を急かすキャラクターではない。
もちろんそれには、エンジンだけではなく、シャーシそのもののセッティングもあるのだろうし、いまどき6速ATだったり、18インチのホイールにあまり扁平率の高くない(235/50R)のグッドイヤー製のタイヤだったり、とそのパッケージによるのだろう。
ハイウエイやバックカントリーをトータル1300kmほどこのクルマを走らせてみて、あぁ、これもアリだなと思う。
クルマに急かされることもなく、それでいて、その気になればマッシヴに加速していくこともできる。
細かなところでは、Apple CarPlayに対応していたり、メーターの照明やアンビエントライトのカラーを変更できたり、ステアリングモードとドライブ・モードが変更できたり(なんとレーストラック設定もある!)、リバースギアに連動したリア・ヴューカメラが装備されていたり、12スピーカシステムの音響がけっこうより良かったり、メートル&リットル / マイル&ガロンの表示切り替えができたり。
何よりもありがたかったのは、クルーズ・コントロール(アダプティヴではないのがなんとも・・・)が装備されていたこと。
それこそ、クルーズ・コントロールに関してはその昔、日本で友人が乗っていたホンダのアコード・エアロデッキにこの機能が装備されていて、スキーにいくのに夜中その友人と交代でクルマを走らせていたとき、日本の交通事情(高速道路含む)でこんな装備必要?使えん、と思ったのが最初。
それからしばらくの後アメリカに来て、オレゴン州ユージーンからルイジアナ州ニューオリンズまで、当時のシェア・メイトと交代しながら一週間ほどクルマを走らせたとき、退屈なハイウエイをひたすら距離を稼ぐシチュエーションで、このクルーズ・コントロールのありがたみが身にしみた。
そして歳月が流れ、東京で乗っていたドイツ車に装備されていたアダプティヴ・クルーズ・コントロールを当たり前に使うようになって、東京〜大阪間を一気に走るようなシチュエイションでは有用な装備だと思うに至る。
まぁ、もう少ししたら、高速道路に関してはほとんどオート・パイロットがスタンダードになるんだとは思うけど。
あと、シート・ベンチレーター機能付きのレザーシート。
これも良かった。
東京の夏、友人が所有するメルセデス・ベンツ・Eクラスに乗ったとき、レザー・シート・ベンチレーターの快適さを知った。
今回のケンタッキー州からテネーシ州への旅でも、東京の真夏と変わらないか、それ以上の気温と湿度。
つまり非常に蒸し暑い状況において、ルームエアコンに加えて、このシート・ベンチレーターがあることにでシートに密着している身体にもあまり汗をかくこともなく、わりと快適に長距離を走ることができた。
アメリカで、しかもハイウエイとバック・カントリー・ロードを組み合わせてそれなりに距離を走るようなシチュエーションだと、このマスタングというチョイスも充分アリだなと思う。
もう少し燃費(オンボード表示で10.8km/Lだった)が良ければいいかな、とは思うけど、途中何時間にも及ぶ大渋滞もあったりしたし、スペックを考えたらそれほど悪い数字でもない、か。
ドイツのプレミアムブランドのクーペとは異なったフィーリングに、また何かの機会に走らせてみたいクルマの一台になった。
しかし、こうなると、俄然シボレー・コルベットに乗ってみたい。
次のフル・モデルチェンジでミドシップ・レイアウトになって、ヨーロッピアン・スーパー・カーと同じカテゴリーになるらしいので、なおさらそう思う。