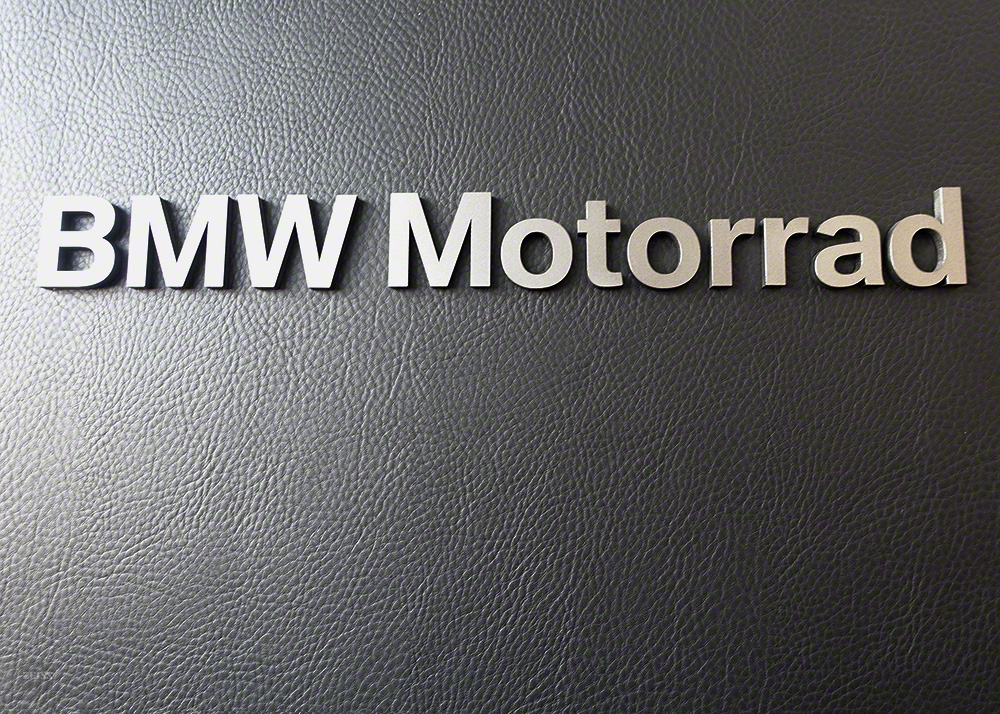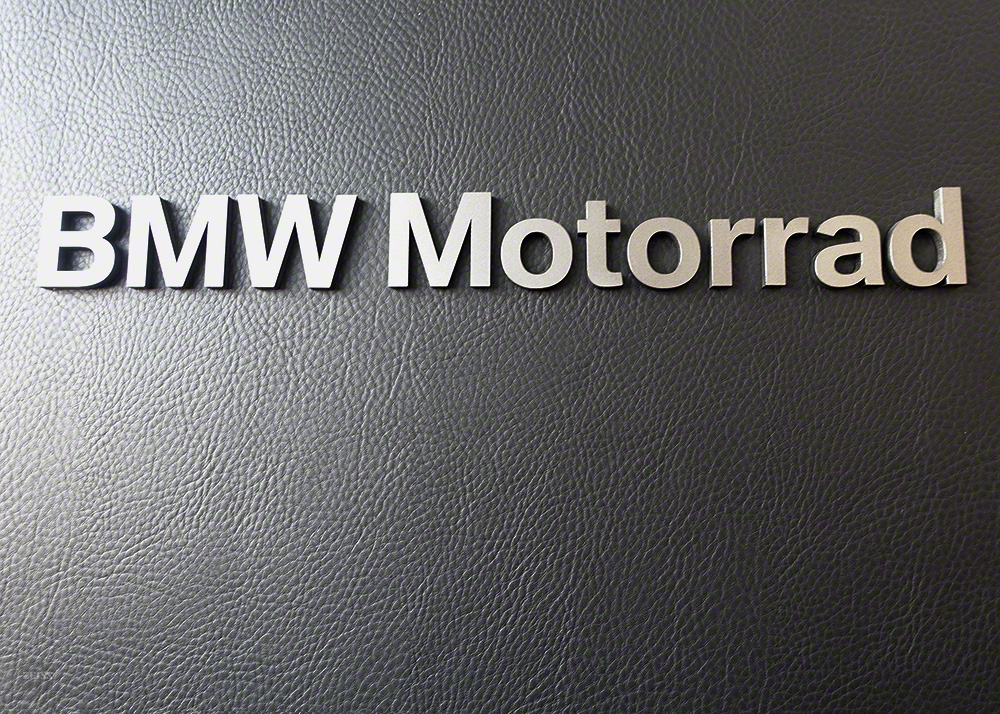








ボクサー・・・といっても、ボクシングのハナシではなく。
レシプロエンジンを使う世界では、水平対向形式のエンジンのことを “ボクサー・エンジン” とよびます。
で、水平対向エンジンといえば、ポルシェ、もしくはスバルのことをイメージするのがこの業界です、現存するエンジンからすれば。
水平対向6気筒のポルシェ・911、水平対向4気筒のスバル・レガシィ。
それぞれキャラクターの立ったクルマ造りをしているように感じるし、タレントがあるようにみえる。
意外かもしれないけど、BMWにもボクサーエンジンを搭載したモデルがある。
2気筒だけど・・・
ちなみに、ホンダにも6気筒のがあるんだが。。。
水平対向エンジン、しかも空冷となれば、それは20世紀の後半でついえたポルシェ911の伝統だろうか。
しかし、21世紀のいまでも、BMWには空冷ボクサーエンジンがを搭載したモデルがある。
二輪だけどね・・・
その噂が世界に拡散したのは、2010年頃だっただろうか、ボクサーエンジンが水冷化される、と。
やがてその噂は現実となり、2013年に水冷化されたボクサーエンジンを搭載した “R1200GS ”がリリースされた。
そして2014年秋、ドイツ、ケルンで開催されたインターモトにおいて、水冷化されたボクサーエンジンを搭載した“R1200R”がアナウンスされた。
年が明けて、2015年3月6日、水冷化されたボクサーエンジンを搭載した “R1200R”のデリバリィが始まったらしい。
これにて、空冷ボクサーエンジンの歴史に幕がおりた、チーン。。
正確にいえば、 “R nine T” という空冷ボクサーエンジン搭載のモデルがあるけど、これはBMW空冷ボクサーエンジンの90周年を記念してリリースされたスペシャルモデルで、連綿と紡がれてきたRシリーズの他のモデルとはちょっと毛色が異なっていて、記念モデルと称してはいても、BMW Motorradの新しいチャレンジといったニュアンスが込められたモデルなので、ココでは除外することにする。
いずれにしても、レギュラーモデルではないし、90周年記念モデルといった体なので、そのうちなくなるでしょう、きっと。
だがしかし、2017年現在、予想に反して、R nine Tシリーズは基本骨格を共通にしたまま、スクランブラーやら、レーサーやら、アーバンやら、ピュアやら、Heritageシリーズとして、完全にひとつのカテゴリィとして独立した存在になってる。。。
ソレって・・・
伝統の空冷ボクサーエンジンが廃止された理由としてはイロイロあるのだろうけど、決定的なのは、2016年からヨーロッパで施行される “EURO4” 規格によるものなんだろう。
つまり、新しい環境基準に空冷エンジンでは基準をクリアできなくなった、そういうこと。
もちろん、性能を落とせば、空冷エンジンでも新しい基準をクリアすることもできるんだろうけど。。
現に、ホンダやドウカティ、モトグッチなどが同時期にリリースした空冷エンジン搭載モデルは、スペックを相当妥協したエンジンになっている。
もちろん、パワーやトルクだけが、そのオートバイの性能ではないのは理解しているつもり。
でも、そのスペック・ダウンを “味” や “ノスタルジィ” といった曖昧な表現で、さも最新ですって飾ってるスタンスには、ちょっと首を傾げたくなる、ただの偏見なんだろうけど。
BMW Motorradはスペック・ダウンして、空冷ボクサーエンジンを延命させようとはしなかった。だから新たに水冷エンジンを開発したわけだし、事実パワーやトルクといったスペックを大幅に向上させた水冷ボクサーエンジンを搭載したRシリーズをリリースしてきたわけだ。
BMW Motorradのそのスタンスには大いに共感するし、新しい時代のボクサーエンジン搭載モデルにも、その将来にもワクワクしてる。
だが、しかし、僕が乗りたかったのは、 “空冷ボクサー” を搭載した“R1200R”だった。
“空冷ボクサー” の“R1200R” が生産中止になったという情報を僕が得たのは、クルマの点検時に訪れたディーラーのごく近くにある、同じ系列のBMW Motorradディーラーだった。
それは夏のはじめ頃のハナシ。
しかし、その時にはそのディーラーには “R1200R”の在庫はなかった。
通常、BMW Motorradでは、いままであったモデルが生産終了になる場合、ドイツ本国のBMW Motorradから日本のディストリビューターであるBMW Motorrad Japanに予め連絡あって、日本として欲しい台数を最後にドイツに発注できる仕組みになっているらしい。
しかし、この“R1200R” に限っては生産中止の連絡がドイツから突然きて、最後の発注リクエストもできなかったらしい。
そして気がついたときには、BMW Motorrad Japanには “R1200R” の在庫はもうなかった。
つまり、あとはBMW Motorrad の日本の各ディラーが店頭在庫だけになっていた。
情報をいろいろ漁って日本にある新車の “R1200R” は3台、ないし4台だった。
東京のディーラーには在庫はなかった。
これを逃すと、空冷ボクサーエンジンを新車で手に入れることは二度とできないんだなぁ、たぶん。。。
そんな2014年、夏もおわりの頃、僕は新車の “R1200R” を手に入れた。
BMWのオートバイに乗る日がくることなんて、ナイと思ってた。
いつか、ドウカティやビモータ、モトグッチには乗るかもとは思ったけれど。。。
BMWとハーレィに乗ることなんて、一生ナイ、そなんふうにぼんやりと感じていた。
オートバイに乗りはじめたコゾーだったころだ。
その頃の僕は、BMWのオートバイって “ダサイ” と思っていたし、小金持ちのオッサンが好むオートバイだと決めつけていた。
まぁ、若さ故のある種の偏見ではあるけど、レーサーレプリカ全盛の時代にオートバイに乗りはじめたコゾーにとって、BMWのオートバイって、その見た目や雰囲気が、ただただオッサンくさいだけだった。
それはとどのつまり、小金持ちのオッサンになったってことか、オレが?
ジーザス・・・
ともあれ、ようやく、やっと、新しい翼を手に入れた!