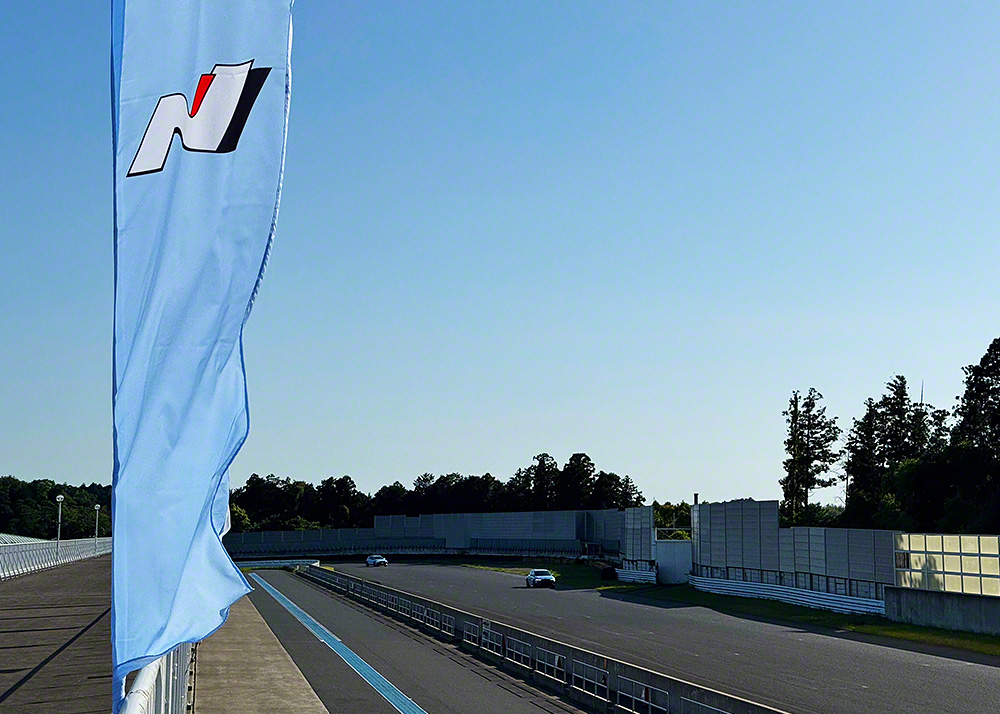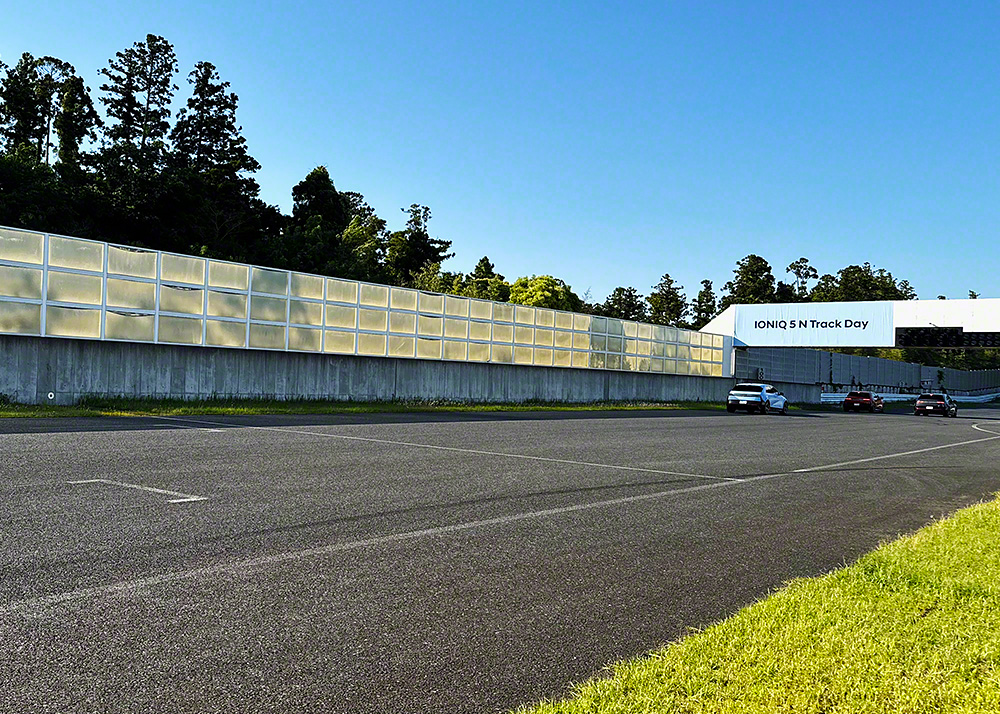CITROËN C5 X
シトロエンにおけるフラッグシップモデル?もしくは一番大きなモデル、そんなC5 Xを300kmほど走らせることができた。
2021年にPSAとFCAがマージしてステランティス・グループになってからシトロエンのクルマに初めて乗った。
サイズ的には所謂 “Dセグメント” といったクルマ。
アピアランスはステーションワゴン・・というのには車高が高いような、SUVと呼ぶのもちょっと違うな。
2022年にリリースされたクラウン・クロスオーバーと同じようなスタイル。
フロア下にバッテリーを敷き詰めるのに都合のいいデザインのように見えるけど、このモデルにはBEVはない。しかしプラグ・イン・ハイブリッドがラインアップされているから、このモデルの企画が立ち上がったときに既にそれ前提でデザインされていたんだろうな。。。
ステランティス・グループのプラットフォーム “EMP2V3” を使うC5 X。
同じステランティス・グループの他のフランス車ブランドであるプジョーには408、DSオートモビルズにはDS4という “EMP2V3” 同じプラットフォームを使ったモデルがある。
そのどちらもが、C5 Xとほぼ同じといっていいプローポーションをしている。
まぁ、今の時代、いろいろな制約があってしようがないんだろうな。
パワートレインはPureTechと自ら呼称する、180PS/250Nmのパワー&トルクを発生する1.6Lの4気筒ガソリン・ターボ・エンジン。1500kg強のボディを走らせるこのフランス車だけど、同じセグメントのドイツ車と較べると、いささか非力に感じる。
確かに速くはないけど、東京都心の流れに乗るのにとりたてて問題ないし、それほどストレスもない。。。
このエンジンにはこれといってドラマもなく、まぁ、フツーっていっていいかな。
数年前、ヨーロッパでシトロエンのクルマを走らせたことがあった。
パリの中心部でピックアップしたそのシトロエンは、なんというかフツーのコンパクト・セダンだった。
日本でいえば、一昔前にあったトヨタのカローラ・セダン、そんなスタンダードな感じ。
いざ、パリの街へアクセラレーターを踏み込みステアリングを切り込むと、大丈夫かこのクルマ?
そんなことを最初に感じた。
ボディに剛性を感じられなくて、ステアリングがダルで、とにかく全体がユルい、なんというか不安で仕方なかった。
ちなみに、クルマをレンタルするとき、僕は可能なかぎり日本やアメリカで乗ることのできないクルマをリクエストすることにしている。
ケオティックなパリ市内を抜け、ル・マン方面へ向かうべくA6へ、そしてA10へと繋ぐ。
高速道路に上がってしばらくは、おっかなびっくりナニもかもがユルいシトロエンを走らせた。
少しずつ速度を上げていくにつれて、シトロエンはヘンな挙動を示すようになっていった。
フランスの高速道路のリミットは時速130km。
パリ市内を流していたときのボディの緩さは遠くに感じるものの、ステアリンとサスペンションの挙動が落ち着いてきて、なんというかスタビリティが上がってピターッと直進安定性が高まってきた。
これうまく説明できないのがなんともだけど、ドイツ車の高速域のオン・ザ・レール感覚のスタビリティとは明らかに違ってる。
うん、でもこれはコレでアリ、気持ちイイ。
シトロエンの代名詞といえば “ハイドロ・ニュー・マチック” でいいだろうか?
諸先輩方がそのシステムを好意的に評価しているのは知ってる。
しかし残念ながら、ソレを装備したクルマに僕は乗ったことがない。
なので、かつてシトロエンが創った、 “魔法の絨毯” と評されたライド感覚とは、それなり、もしくはずいぶん違うのかもしれないけど、僕には判断できない。。。
・・・そんな数年前の記憶と感触を期待して、C5 Xを走らせた。
確かにソフト、柔らかい挙動と乗り心地。
しかし、イメイヂしていたシトロエンぢゃない。
なんというか、ただ柔らかいだけ。
高速に上がってアクセルを深く踏み込んでいくも車速相応にスタビリティが整っていく感覚はあまりない。不安定なフィーリングというわけではないけど、低速走行時のユルい感じのまま、車速が上がっていくだけ、これといったドラマは、ない。
それなら、低速時はどうだろう、交差点、前走車の減速にシンクロさせるようにブレーキ・ペダルを柔らかく踏んでいく、フロントノーズを沈み込ませながら車速が落ちていく。
やがてC5Xは停まる、いくつかのピッチングを残したまま・・・
うーん。。。
100年に一度の激動の時代といわれる自動車業界。
そのウェーヴのなか、新興企業、吸収合併、提携などなど・・・
その結果として、グループ内で共有されるプラットフォームやパワーソース、補機類や電装系、ADAS等の各マテリアルが最大公約数的に共通化されることによって、かつてそれぞれのブランドが持っていたキャラクターが薄まってしまうのは必然なのだろうな。