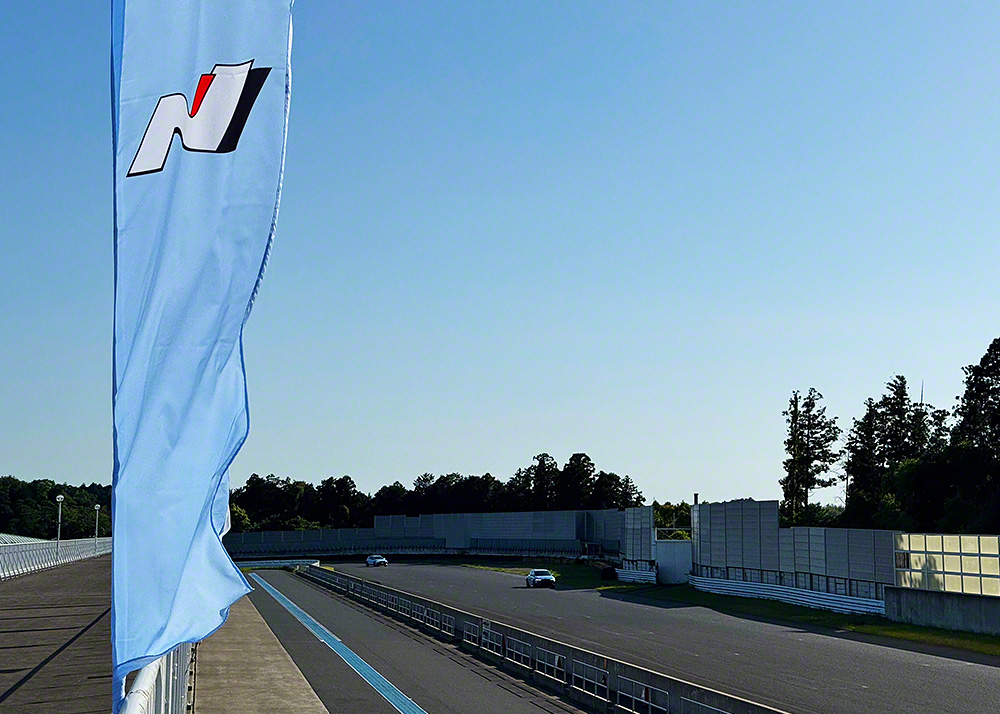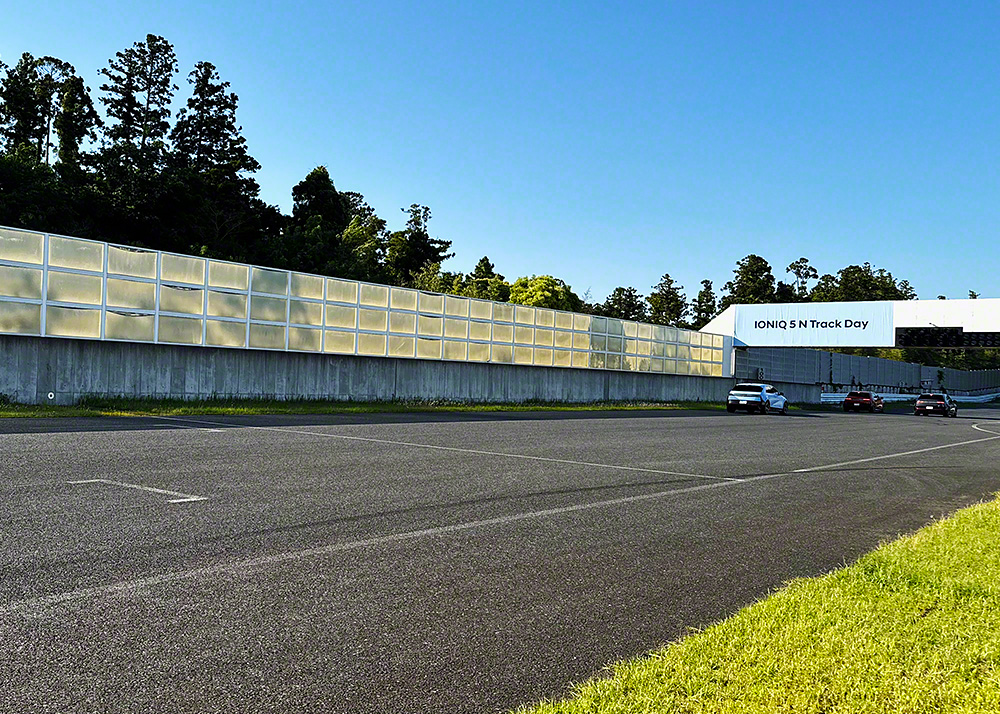HYUNDAI IONIQ 5 N
まぁ、なんにせよ、フツーにDセグメントあたりのSUVを走らせるようにレーストラックを走らせることができた、そういうこと。
・・・まぁ、それが好きかどうかは別にして・・・
キレイに晴れた5月の空の下、クローズドコースで気兼ねなくクルマを走らせる。
いいイベント、いいクルマでした。